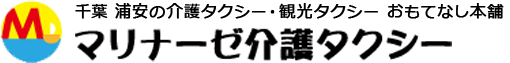習志野市 津田沼駅前「BOOKS昭和堂」、閉店までの舞台裏
9月15日、千葉県習志野市のBOOKS昭和堂が閉店した。JR津田沼駅の改札口から至近という好立地に加え、品ぞろえと接客の丁寧さなどにも定評があり、インターネット上には多くの惜別の声があがった。
BOOKS昭和堂といえば『白い犬とワルツを』(新潮文庫)を思い浮かべる人も多い。
同書がBOOKS昭和堂で多く売れていることがニュースになったのは、刊行から3年を経過した2001年夏。新潮社は、同店の書店員・木下和郎氏による手書きのPOPに効果があると見て、これをコピーし、全国の書店に販促物として配った。『白い犬とワルツを』は、それから半年ほどで150万部に達するミリオンセラーとなった。
■手書きPOPを定着させた『白い犬とワルツを』
書店員が熱意を込めて推した本は売れる――それ以前から行われてきたことではあったが、手書きPOPが販売促進の手法として認知され、現在まで定着することになったのは、あきらかにこれがきっかけだった。
だが、当の木下氏がこのブームを否定していたこと、やがてPOPを書かなくなり、書店の現場から離れていったことは、あまり知られていない。
運営する大和商事はパチンコ店や居酒屋などを多角的に展開。BOOKS昭和堂は自社ビル内で営業していたが、それでも赤字事業となっていたようだ。跡地にはテナントを誘致する予定だという。
BOOKS昭和堂の売場面積は約100坪。新刊書を扱う書店が増えていた1990年代半ばまで、これは少ない人員で一通りのジャンルを扱える、スタンダードな広さだった。
だが、とくに2000年代に入ってからは、この規模の書店が続々と閉鎖している。いまの主流は、贅沢なデザインを施した空間に大勢の客を取りこむ1000~2000坪級の超大型店か、1~2人でも運営できる極小規模店である。本が次第に売れにくくなっていくなかで、ある程度の運営スタッフを必要とする中規模店は利益を確保しにくい。BOOKS昭和堂の場合は、社員4人、アルバイト10人ほどの人員体制だったという。
オープンは1986年。けっして短い営業年数ではない。月並みな表現になるが、時代の変化とともに役割を終えたと見るべきなのかもしれない。
閉店を1週間後に控えたBOOKS昭和堂を訪れた。木曜の夜も、土曜の昼下がりも、すくなくとも僕が滞在した時間、客は少なかった。もっとも、最奥の児童書売場では子どもたちが床にしゃがんで絵本を開き、その母親たちものんびりと雑誌をめくっていた。地域の人たちにとって気軽に立ち寄れる書店だったことをうかがわせる光景だった。
閉店の理由は、業績の低迷だという。昨年1月から店長を務めた村山智堅氏は「4~5年前から売り上げの低下が顕著になった」と話す。
「手をこまねいていたつもりはないんです。アウトレット本(=出版社が再販指定を外して廉価販売する本)を扱ったり、ゆっくり過ごしていただけるベンチを置いたり、文具も扱ったり。ただ、肝心の本の売れ方が弱くなった。注目度の高い新刊が出ても3~4日で動きが止まってしまう。こちらからの仕掛けも、なかなか伝わらない。私の力不足も認めなくてはいけない。全国には、同じ状況で奮闘している書店がありますから。でも現場を預かる者の実感として、閉店の判断はやむをえないと思っています」
村山氏に、かつて一緒に働いていた木下さんのことを、同じ書店員としてどう思っていたのか、きいてみた。
「考え方の違う人でした。私は、本屋は特別な商売ではない、世の中にある多くの商いの1つと考えてきました。木下は、本屋は本をどう扱うべきかを、深く突きつめて考えていた。だが、狭すぎるのではないか、とも思っていました」
村山氏は、大学時代のアルバイトからBOOKS昭和堂に勤めてきた。6歳年上の木下氏とは長く上司と部下の関係にあり、書店員の仕事を教えてもらった人だという。すでに退職した木下氏のことを、いまも対外的には「木下」、顔を合わせたときには「店長」と呼んでしまう。
「『白い犬とワルツを』が売れはじめた2001年頃は、私が文庫売場の担当でした。POPを立てて、それが売れるようになった段階までは、木下も楽しんでいたと思います。ただ、その後の急激な売れ方、メディアによる『白い犬とワルツを』や木下の取りあげ方は、たしかに異常ではありましたね」
出版社が刊行した本を書店が仕入れて売る、いわゆる新刊書の市場は、統計上は1996年をピークに右肩下がりとなっており、出版業界は打開策を求めていた。『白い犬とワルツを』のヒットをきっかけとした「現場で本を売っている書店員こそが市場回復のキーマン」というストーリーは、多くの人に伝わりやすいものだった。なお、全国の書店員の投票で決める「本屋大賞」が誕生するのは、2004年のことである。当時、出版業界の専門紙で記者をしていた僕も、こうした現象を積極的に記事にした。
■「書店員推薦」に警鐘を鳴らした
だが、”カリスマ書店員”として寄稿やコメントを求められるようになった当の木下氏は、一貫してそうした風潮を否定する主張を続けた。
〈読者が自分ひとりかもしれないという本にこそPOPを書く〉
〈新しさや部数の大きさでしかものを測れない人を軽蔑してください〉
〈「手書きPOPからベストセラー」は矛盾です〉
これは当時、ある媒体で木下氏が同業の書店員に向けて書いた文からの抜粋である。
出版社が推薦を頼んできても受けてはいけない、受けてしまった場合は駄作なら駄作とはっきり言おう……。『白い犬とワルツを』をきっかけに”書店員推薦”を宣伝に利用するようになった出版業界に、木下氏は警鐘を鳴らした。
本は「商品」である前に「作品」である。書店員は、まず「作品」としての本と誠実に向き合わなくてはいけない。彼は、そう伝えたかったのだと思う。だが、1冊でも多く売ることで成り立つ出版業界において、そのメッセージはやはり『白い犬とワルツを』のPOPと違ってほとんど波及しなかった。
やがて、木下氏はPOPを書かなくなり、メディアへの登場機会も減っていった。BOOKS昭和堂を退職したのは、2016年1月のことである。
職場内で、木下氏と考え方を共有していた人はいたのだろうか。
「根本的には、1人もいなかったと思います。もちろん、本屋は本を売ってさえいればいいのか、という問いを抱えることは大切です。でも私は、できるだけ多くのお客様に手にしていただけるような選書とお薦めをしたかったし、作品としての良し悪しより、売れる本を前に出すことを優先する場面も多かったと思います」(村山氏)
だが本屋の存在意義は、そうした職業意識的な言葉だけでは語りきれない。
■作品でも商品でもある本といかに向き合うか
9月1日から閉店まで、村山氏は「私達 この本が 大好きです」と題したフェアを店の入り口付近で大きく展開した。来店客に薦めて好評を受けた本、思うように売れなかったが大切に扱ってきた本……その1冊1冊に、村山氏やスタッフの直筆POPがついていた。
閉店直前の書店がこうしたフェアを実施することは多い。最後を迎えたとき、本屋はたんなる本の販売員ではなくなる。本が「商品」である前に「作品」であることに、より忠実になる。ラインナップのなかには『白い犬とワルツを』もあった。当時の木下氏が書いたコメントを再現したPOPが添えられていた。
収益を確保できなくなれば、書店は営業を終える。通い慣れていた客はいっとき困るだろうが、本を手に入れる方法は、ほかにいくらでも残っている。
だが、「作品」であり「商品」でもある本を、どう扱うか? この問題と向き合い、懊悩しながら棚に並べる1冊1冊を選択してきた本屋たちの仕事は、代わりがない。