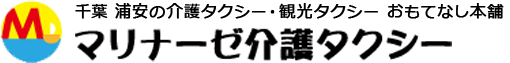千葉市
自閉症児と母の17年を追って学んだこと 「普通」を捨てて、我が子のために人生の目標を設定する
私は、千葉市の中心部からやや離れたところに小児クリニックを構える医師です。
大学病院に在籍していた頃は、小児固形がんを専門として、19年間にわたり基礎研究と臨床の両面で体力の限界まで小児外科医として働いてきました。文字通り体力の限界を超えた私は大きな病気を患い、メスを捨てて開業医になりました。
そして空いた時間を利用してささやかながら執筆活動をしています。本稿では、自閉症児の成長の記録を聞き書きした中で、自分自身が学んだことを、自分の子どものちょっとした「困難」も交えて書いてみたいと思います。
【寄稿:松永正訓・松永クリニック小児科・小児外科院長】
自閉症という障害は社会的な障害
知的遅れのある自閉症児の成長記録を書くことは長年の私の希望でした。私はこれまでに、短命という運命の障害児の記録や、自宅で呼吸器を付けた子の記録を書いてきました。
もちろん、障害の重さに「軽重」などありません。それぞれのご家庭が大変な思いを抱えています。
ただ、知的障害児には体が元気であるという特徴があります。私のクリニックにも何人もの知的障害児が風邪をひいて受診をしますが、クリニック中を走りまくったり、大きな声を上げたりすると、母親の神経は休まらないように見えます。
社会との接点が多く、そのたびに衝突をくり返す知的遅れの子は、寝たきりの重症児を持つ親とはまた違った種類の苦労があるのだろうと私は以前から思っていました。さらに自閉症という障害は、社会的な障害と言えます。
その主な障害は二つあります。
一つはコミュニケーションの障害です。人に関心を持たない自閉症児は、自分の母親ともコミュニケーションを取ろうとしません。他人の心を理解することにも障害がありますから、人間関係の構築が極めて困難です。
そしてもう一つは、同じものに興味が集中してこだわりから抜け出せないことです。このこだわりの強さは、家庭の中でも社会の中でも大きなトラブルになります。
私がこれまでに書いてきた障害児のルポルタージュも、メインテーマは障害児を受容する親の気持ちでした。知的障害のある自閉症児を受け入れる親の気持ちをどうしても知りたいと考えていた時に、偶然、立石美津子さんという女性と知り合いました。
子どもを「普通」に育てる夢
立石さんは幼児教育に関する著者・講演家です。そして知的遅れのある自閉症の息子さんをシングルマザーとして18年育てています(本書執筆時は17歳)。以下、立石さんのことを母と、お子さんの名前を勇太君(仮名)と書きます。
私は、聞き書きという形で母から見たお子さんとの17年間を描くことにしました。
予測をしていたこととは言え、母は我が子の障害を簡単には受け入れませんでした。こどものこころ診療部の専門医に、2歳の勇太君のことを「知的障害を伴う自閉症」と診断された時、母は医師に対して怒りの気持ちを抱きます。そして同時に我が子に対して「こんな子は要らない」と拒否感すら持ちます。
母は自分の親から英才教育を受けて育ったため、勇太君にも英才教育を施していました。勉強ができて、いい学校に行って、いい会社に入って、いい家庭を築くことは、母にとっての夢だったのです。
しかしこの夢はよく考えてみれば、私たちの誰もが頭の中に描く夢です。そういう意味では「普通」の夢です。
「普通」であることを否定されそうになった母は、医師の診断を誤診だと考え、ドクターショッピングに走ります。5つのクリニックや病院を回って、母は自閉症という診断を認めざるを得なくなります。
しかし、だからと言って勇太君の未来を諦めてしまうわけではありません。2つの施設に通って療育を受けるのです。療育とは、発達を促し、自立した生活ができるように援助をすることです。
けれども、勇太君を「普通」の子にすることはできませんでした。療育の成果はありましたが、勇太君はあくまでも知的遅れを伴う自閉症児なのです。
保育園に通う勇太君はみんなと同じ行動が取れません。一列に並んで同じ格好をして歌を唄う子どもたちと離れ、勇太君は一人で絵本を眺めています。
その姿を見て、母は絶望的な気持ちになります。この気持ちから母はなかなか抜け出すことができず、抗うつ剤を内服することになります。
親の方が変わる 我が子の障害を受容するとは?
ではなぜ、母は我が子の障害を受容できたのでしょうか? それは偶然ある日、精神科病院の鉄格子の向こうに小学生くらいの子どもが佇んでいるのを窓の外から見てしまうからです。
その病院は、適切な育児を受けなかったためにストレスが昂じ、うつ病や統合失調症を併発してしまった自閉症児を「収容」していることで知られていました。
母は見知らぬ少年の悲しい姿を見て、ようやく我が子が「普通」に生きていくことを諦めるのです。
障害児を授かる親の心理的変遷を分析した専門家の報告は多数ありますが、ある学者は、障害児の誕生を母親にとっての「期待した子どもの死」と見なしています。
死の受容。それは決して簡単なことではありません。ある精神科医は、死の受容を5段階で表現しました。否認・怒り・取引・抑うつ・受容です。
確かに勇太君の母も、誤診と思い(否認)、ドクターショッピング(怒り)をし、療育に期待し(取引)、保育園での孤立に絶望し(抑うつ)、鉄格子の奥の少年を見て(受容)に至ります。
ですが、死の受容とは「諦め」であって、障害児を育てるためには「諦め」の先があるはずです。
つまり障害を生きるという人生が待っているのです。このためには、今まで持っていた古い価値観を捨てて、新しい価値基準を構築して、我が子に対して「あなたは、あなたのままでいい」と承認する必要があります。
この作業は、まさに「普通」であることの呪縛を断ち切り、「世間体」とか「世間並み」といった横並びの生き方と決別し、我が子にとって最も幸せな生き方を理解し、寄り添い、伴走することです。
障害を持った子どもを変えようとしてはいけない。親自身が変わらなくてはいけないのです。
健常児の子育てとつながる課題
私は聞き書きを進めるうちに、知的障害のある自閉症児を受容し育てるということには、健常児の子育てにつながる課題があることが見えてきました。
私の知人のお子さんの中には、いじめに遭って登校拒否になった子、病気によって友人との関係が作れず高校を中退した子、両親の不仲から問題行動に走った子など、難しい生き方をしている子が多数います。
いえ、そこまで深刻でなくても、勉強が苦手だとか、親友ができないとか、家族関係がギスギスしているだとか、生きづらさを抱えている子どもはいくらでもいると思います。
そうした時に、私たちが考えがちなのは、「せめて世間並みという『普通』の基準から滑り落ちない」ということではないでしょうか。
しかし「普通」にいくらしがみついても、そこから脱落し、違った道を歩まざるを得ないのも、また人生ではないでしょうか。
性同一性障害と明らかになった私の子ども
個人的な話になりますが、私の子どもも「普通」の道を歩んでいません。
現在15歳になるヒカリ(仮名)は、女の子として生まれ、小学3年生までは「普通」の女の子でした。しかしその後、心の性と体の性がバラバラになり、性同一性障害ということが明らかになりました。
小学生の時のヒカリは中性のような存在としてみんなに受け入れてもらえました。中学校からは、電車とバスで1時間ほどの中高一貫校に進むことになりました。
最大の問題は制服とトイレでした。どうしてもスカートを穿くことができないヒカリに対して学校は理解を示してくれ、詰め襟の学生服の着用やヒカリ専用のトイレまで用意してくれました。
こうしてヒカリは男子として学校に通うようになりましたが、カミングアウトでつまづきました。入学式で校長先生からヒカリの性同一性障害について説明はあったものの、中学生になったばかりの生徒たちには理解を超えていたのです。
ありのままでいられず、クラスメイトとの間に透明な壁ができていった
本当の自分を明かせない苦痛
ヒカリは学校で男子としてとおっていましたので、今さら自分が本当は女子であるとは言えなくなってしまいました。本当の性を明かすと友人が去っていくと恐れたのです。また自分は友人を騙しているという罪悪感にとらわれました。
友人と腹を割って話すということができず、しだいにクラスから孤立していきました。朝、学校に着いても話す友人がいないため、学校の周囲を始業時間になるまで何周もグルグル回っていたそうです。
人の中に入ることが辛くなり、電車やバスも怖くなりました。人混みにまぎれると、心臓がドキドキし気分が悪くなるのです。パニック障害でした。
およそ半年間をかけて大学病院の認知行動療法のセッションにヒカリと妻は通いました。これによってパニックはやや軽減しました。
しかしどうしても教室に入ることが怖くて足が竦んでしまうのでした。この状態にヒカリは精神が不安定になり、毎晩のように泣きました。まさに「普通」から脱落しかかっていたと言えます。
私が学会で自宅を留守にした時、妻からメールがありました。あまりにもヒカリが不安定なので精神科を受診して「クエチアピン」という薬を処方されたと聞かされました。私はその薬の名前を聞いたことが無かったので、すぐにスマートフォンで調べました。
クエチアピンの添付文書はすぐに見つかりました。効能・効果には「統合失調症」と書かれていました。保険病名とは言え、この言葉は私の胸に刺さりました。
ヒカリは今年度で高校を中退することになります。自宅で自習して高卒認定試験を受け、2年後に大学受験に挑む予定です。大学には制服がありませんから、小学生の時と同じように、中性として周囲から受け入れてもらえるかもしれません。
ここに至るまでの心の整理を付ける過程で、家族で何度も話し合い、泣いたり、慰め合ったりしながら何とかやって来ました。
「普通」ではない人生、「生産性がない」人生
ヒカリの将来はどうなるのでしょう? それは誰にも分かりません。
ヒカリにはまだ恋愛経験がありませんので、男性を好きになるのか、女性を好きになるのかまだ分かっていません。もし女性を好きになれば、いま問題になっている言葉を使えば「生産性がない」ということになります。
「普通」ではない人生、「生産性がない」人生。
それってそんなに惨めなものでしょうか?
「普通」でなくても、「生産性」がなくても、親から見れば我が子は何物にも替え難い唯一無二の存在です。そういう人生を他人が貶めるのは、かなり軽率ではないでしょうか?
最初は「こんな子は要らない」と勇太君を拒否した母は、今では勇太君を溺愛しています。どういう変化が起きたのでしょうか?
それは我が子を愛するのに最初は「条件」が付いていたからです。可愛い子、頭のいい子、人より優れた子、そういう子どもが欲しかった。つまり条件付きの愛だったのです。
しかしその愛はやがて「無条件の愛」に変わっていきます。人は育てる中で、初めて親になっていくのです。親は自分の子どもをありのまま愛する能力を少しずつ育てていけるのだと私は思います。
本書を最後まで読んで頂くと、母には勇太君の未来に関して明確な目標を持っていることが分かります。単なる夢ではありません。勇太君が幸せに人生を歩んでいくために、成し遂げなければいけない目標なのです。
目標を設定して生きるその道のりは、容易ではないかもしれませんが、生きがいのある充実したものではないでしょうか。
立石美津子さんに聞き書きして作った本書は、私の家族に生きる勇気を与えてくれました。
新作の主人公である立石勇太さん(真ん中)、美津子さん(左)親子から、筆者(右)は多くのものを受け取った
私にとって学びの連続でした。障害児がやがて大人になって、最終的に就労するとか、税金を納めるとか、それはどちらでもいいことだと私は個人的に思っています。障害児が生きることで、いや、ただ存在することだけで私たちは多くの学びと気づきを得ることができるからです。
東京都自閉症協会は、相模原障害者殺傷事件から2年が経ったこの夏に声明を出しました。その中にこういう文章があります。
「障害者の幸せはあらゆる人の幸せにつながっている」
私もそう思います。この世の中で最も弱い人たちを守れなければ、私たちは幸せになれないのではないでしょうか?
立石美津子さんに聞き書きして書いた『発達障害に生まれて 自閉症児と母の17 年』
Tadashi Matsunaga
立石美津子さんに聞き書きして書いた『発達障害に生まれて 自閉症児と母の17 年』
【松永正訓(まつなが・ただし)】松永クリニック小児科・小児外科院長
1961年、東京都生まれ。1987年、千葉大学医学部を卒業し、小児外科医となる。日本小児外科学会・会長特別表彰(1991年)など受賞歴多数。2006年より、「松永クリニック小児科・小児外科」院長
『運命の子 トリソミー 短命という定めの男の子を授かった家族の物語』にて2013年、第20回小学館ノンフィクション大賞を受賞。著書に『呼吸器の子』(現代書館)、『発達障害に生まれて 自閉症児と母の17年』(中央公論新社)など。