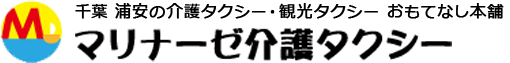船橋市
約15年の執念が結実! 『オボの声』齋藤孝監督と主演の結城貴史、共演の水野美紀に訊く
『ビルと動物園』などを発表している齋藤孝監督が、松田優作賞優秀賞を受賞した自らのオリジナル脚本を映画化した『オボの声』。優れたシナリオに与えられる賞の受賞脚本の映画化となると、順風満帆な映画企画の成立に思えるかもしれない。だが、本作はふたりの男の執念の結実とでも言おうか。約15年に及ぶ悪戦苦闘があった。映画化を諦めなかった齋藤孝監督と、瀬々敬久作品など多数の映画でバイプレイヤーとして活躍してきた主演の結城貴史、ふたりを見守り続けた水野美紀がここまでの道のりを振り返った。
今回の齋藤監督のオリジナル脚本が松田優作賞優秀賞に輝いたのは2013年のこと。だが、実のところ脚本はさらに遡ること約10年前、齋藤監督と結城が出会った直後に出来上がっていたという。
齋藤「出会いはお互いまだ20代の15年ほど前。当時、僕は自主映画を作り始めたときで、彼が出演してくれて初めて顔を合わせました。印象をひと言で表すなら“やんちゃ”(笑)。本人も実際にそういう、まあ無軌道な若者役をやることが多いと。ただ、僕はもっと違った魅力のある役者のような気がして。で、ある時、彼がうちに遊びにくると。その際、彼を念頭に当て書してひと晩で完成させたのが今回の脚本。だから15年前にすでに脚本はあったんです」
結城「監督とは歳が同じということもあって、なにか波長が合って。それで家に遊びにいったら、この脚本があった(笑)。自分のために書かれた脚本にお目にかかったのはこの時が初めてだったし、素直にうれしかった。当然、“形にしたい”と思いましたよ」
ふたりで映画化へ向けて動き出したとき、まず脚本を見せたのが結城と親交のあった水野だった。
結城「お美紀とは、お互い役者として出会っているんだけど、クリエイターとしてより親しくなったというか」
水野「そうだね。俳優仲間というよりは、同じモノづくりの人間という立場で話す機会が多かった。私が演劇ユニットを組んだとき、アトリエ兼事務所のようなスペースを借りたんですけど、そこをシェアした仲間のひとりが結城くんで。一時期、デスクを並べていた時期もあったよね(笑)」
結城「僕は映画の制作会社を立ち上げ、お美紀は演劇ユニットでワークショップをやったりして。僕がお美紀の開いたワークショップに参加したり、逆にお美紀の仲間に僕の作品に出てもらったりと、クリエイターとして互いに向き合い、いろいろと深いところまで意見を交わすようになった。そういう時間があったから、ある意味、僕にとって水野美紀は信頼の置けるいわば同志で。かつ一度は役者として組んでみたい気持ちもあった。それで脚本を見てもらおうと。恵比寿で火鍋を食べながら、脚本を見てもらいました」
齋藤「気づいたときには水野さんが会計を済まされているという(苦笑)。こちらが呼び出しておきながら、僕らがごちそうになってしまうという失礼な会合だったんですけど」
水野「そうでしたっけ。まあ、私としては監督からも結城くんからもその熱意が伝わってきたので、スケジュールさえあえば出演は問題ないと。私にできることならば応援したいと、それだけでしたね」
ただし、そう簡単に事は運ばない。当たれるだけのところには当たったがどこも映画化に動くまでには至らず仕舞い。だが、諦めずに、結城の年齢があがれば、その年相応の役の人物像と内容に脚本を書き直し、チャンスを待った。その間にチャンスはなかったわけではない。時には主人公の設定を変えたら映画化OKの話や、主演が別の俳優ならばという話も舞い込んだ。しかし、齋藤監督はこれらのオファーに同意せず、最後まで結城主演で撮ることにこだわった。もう半ば無理だろうと、齋藤監督は監督業を辞めて就職した時期もある。こうした紆余曲折の末、完成を迎えたのが今回の作品になる。
水野「忘れたころに松田優作賞優秀賞を獲ったと連絡がきて、それからまた音信不通に。すると、また忘れたころに“映画化が決まった”と連絡がきた(苦笑)。ほんとうに今にも切れそうな糸をどうにか途切れさせずににここまでたどり着いたよね。こういう場合、流れることがほとんどだから」
結城「この業界に身を置いてるとわかるけど、9割方消えるパターン。だから、別の俳優でと話がきたときは、監督に申し出た。“こんなチャンスないから、俺のことは気にせずに受けろ”って。でも、監督は断った。そこからはもう意地というか。こいつが俺に懸けてるんだから、俺もその期待に応えないとと。人生懸ける感じでしたね」
齋藤「一時期、監督業から離れたけど、やっぱり舞い戻ったのは、この企画だけは絶対にやり遂げないとと思ったから。これだけは形にしたかった」
もはや執念で出来上がった作品は、鳴かず飛ばずの人生を送ってきた40代の元ボクサーの苦悩と葛藤を骨太に描いた濃密な人間ドラマ。結城は主人公の秀太を演じた。
結城「クランクイン前に、ロケ先に行って“いよいよか”とこみあげてくるものがあったのは確か。ただ、逆に15年も経つと、へんな気負いはなく、実際の撮影には平常心で入れたというか。誰よりもこの脚本を読みこんでいる自信があったし、世界で一番この本を読んでいる自負があったので、力は入りましたけど、ミスすることを恐れることはなかったですね。事前にやっておいたのは、秀太という人間の器を作っておくこと。共演者のみなさんとの芝居は現場で作っていけばいい。けれども、秀太という人間と周りを納得させるものを作っておかないとと。ボクサーですからまずシャープなフィジカルにしないといけないと思い、実際にボクシングジムに通って12キロ体重を落としました。でも、監督からは“そこまで落とさなくていい”と言われて結局、2キロぐらい戻したりしたんですけどね(笑)」
水野「減量していたのをまったく知らなかったから、現場で会ったときはびっくり。様子が全然かわっていたから。体中からほんとうに伝わってきました。この役に取り組む本気度が」
一方、水野が演じたのは妊娠が判明した秀太の恋人。将来が描けないでいるふたりは、子どもを産むか生まないかで対立する。不思議なめぐりあわせで、当時、水野も実際に妊娠が判明した直後だった。演じる際、結城と水野の間ではこんなやりとりがかわされたという。
結城「お美紀に呼び出されたんですよ。待機中の車の中に」
水野「そのときのこと、よく覚えていないの(笑)」
結城「そこでひと言“私、妊娠したから”と。その私にむかって“堕ろせって言うんだからね”と言われて、いやあ自分が試されるなと思いましたよ。一気にそれでスイッチが入ったというか。このシーンは心して挑んだシーンになりました」
水野「私としては恋人同士の役だったけど、険悪なムードになっている関係で良かったかなと。お互いのことをよく知っている分、仲の良いカップルだったら、ちょっと恥ずかしかったかも。あと、撮影のスケジュールがずれていたら、出産で出演が叶わなかったので、無事出演できたことに安堵しましたね」
水野が演じた秀太の恋人は、産むことを決意。その現実から逃れるように秀太は故郷へひきこもる。物語は、その故郷で見つけたアルバイト先で秀太が人殺しと噂される守義と出会い、一緒に働く中で、自身の人生を振り返り、何か活きる術を見つけていく。その心の軌跡を結城貴史という役者の体内から湧き出てきたモノで伝える。けっして明快でわかりやすい映画とはいえない。ただ、誰にでも経験のあるままならない事態へのいら立ちややるせなさ、自分自身への怒り、漠然とした将来への不安といったことがリアルにこちらに伝わってくるはずだ。
水野「私はどうしても女性の目線に立ってしまうのだけれど、40歳を過ぎた男が、恋人の妊娠を知ったら、家を出て行っちゃうって、もう最悪ですよ。とても彼に共感なんてできない。ただ、物語はそうなんですけど、映画自体はワンシーンワンカット、音楽なしで、それこそ服がちょっと擦れる音から、ごはんを食べる音とか、すべてが生々しくリアルにこちらに伝わってきて、なにか自分もその場に一緒にいるような気分になってくる。もっと言えば、登場人物と同じように呼吸し、行動している感覚になるぐらい引きこまれる自分がいました」
結城「秀太はいろいろなものを抱えて、最後は抱え込めなくなって恋人からも自分の人生からも逃げ出していく。僕自身、好きな人間かと言われれば同意しかねる。ただ、40代に入ると諦めることが多くなるというか。いろいろな意味で若い頃は立ち向かえていたことにも、立ち向かう気力がなくなってしまうことがある。場合によっては、感情を押し殺さないといけないときもある。その気持ちはちょっとわかるかなと。秀太の気持ちに多くが共鳴するとは思わない。けれども、共有するところはあるんじゃないかな。そういう意味で、自分も40代になったいまだからこそ演じられた役といっていいかもしれない。なにも感情を激しく露呈するだけが、その想いを伝えるわけではない。そういうことが30代半ばぐらいから、ようやくわかってきた。そこを経てきたからこそ演じられた気がする。また、お美紀をはじめ、菅田俊さん、石倉三郎さんら声をかけたみなさんが快く出演してくださった。このことにも感謝です」
齋藤「明るいとは言い難い内容なのですが、薄いですが光が差す瞬間がある。そこをみていただければと。現実から逃げることは彷徨うことでもある。これからの人生や生き方に彷徨っている人に観てもらえたら、なにか心にひっかかるものがあるのではないかと思います。最後に、ほぼ全編のロケ地で、全面協力してくれた長野県箕輪町、千葉県船橋市のみなさんにも感謝したい。僕も結城も昔の映画というか。町ぐるみ、もっといえば地元の人と映画のスタッフとキャストが上下ない関係で一体となって映画を作る。そういう映画を作ることがひとつ夢としてありました。今回、それが実現できた気がします。地元のみなさんのマンパワーがなかったら、この映画は完成しなかったかもしれない。15年かかりましたけど、いまはこれほどないというぐらい幸せな形で作品が完成したなと思っています」