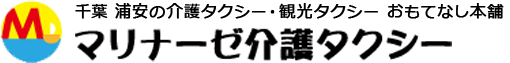松戸市 二十世紀梨
ナシ(和なし、日本なし)は、中国を原産とし中国や朝鮮半島、台湾、日本の本州、四国、九州に生育する野生種ヤマナシ(ニホンヤマナシ、P. pyrifolia var. pyrifolia )を基本種とする栽培品種群のことである。
高さ15メートルほどの落葉高木。葉は長さ12cm程の卵形で、縁に芒状の鋸歯がある。花期は4月頃で、葉の展開とともに5枚の白い花弁からなる花を付ける。8月下旬から11月頃にかけて、黄褐色または黄緑色でリンゴに似た直径10 – 18センチメートル程度の球形の果実がなり、食用とされる。果肉は白色で、甘く果汁が多い。リンゴやカキと同様、尻の方が甘みが強く、一方で芯の部分は酸味が強いためあまり美味しくない。しゃりしゃりとした独特の食感がナシの特徴だが、これは石細胞と呼ばれるものによる。石細胞とは、ペントザンやリグニンという物質が果肉に蓄積することで細胞壁が厚くなったものである。これは洋なしにも含まれるのだが、和なしよりもその量が少ないために、和なしと洋なしとで食感に大きな差が生じる。
野生のもの(ヤマナシ)は直径が概ね2 – 3センチメートル程度と小さく、果肉が硬く味も酸っぱいため、あまり食用には向かない。ヤマナシは人里付近にしか自生しておらず、後述のように本来日本になかった種が、栽培されていたものが広まったと考えられている。なお、日本に原生するナシ属にはヤマナシの他にもミチノクナシ(イワテヤマナシ) (Pyrus ussuriensis var. ussuriensis) 、アオナシ(Pyrus ussuriensis var. hondoensis、和なしのうち二十世紀など果皮が黄緑色のものを総称する青梨とは異なることに注意)、マメナシ (Pyrus calleryana) がある。
日本でナシが食べられ始めたのは弥生時代頃とされ、登呂遺跡などから多数食用にされたとされる根拠の種子などが見つかっている。ただし、それ以前の遺跡などからは見つかっていないこと、野生のナシ(山梨)の自生地が人里周辺のみであることなどから、大陸から人の手によって持ち込まれたと考えられている。文献に初めて登場するのは『日本書紀』であり、持統天皇の693年の詔において五穀とともに「桑、苧、梨、栗、蕪菁」の栽培を奨励する記述[2]がある。
記録上に現れるナシには巨大なものがあり、5世紀の中国の歴史書『洛陽伽藍記』には重さ10斤(約6キログラム)のナシが登場し、『和漢三才図会』には落下した実にあたって犬が死んだ逸話のある「犬殺し」というナシが記述されている[3][4]。
江戸時代には栽培技術が発達し、100を越す品種が果樹園で栽培されていた。松平定信が記した狗日記によれば、「船橋のあたりいく。梨の木を、多く植えて、枝を繁く打曲て作りなせるなり。かく苦しくなしては花も咲かじと思ふが、枝のびやかなければ、花も実も少しとぞ。」とあり、現在の市川から船橋にかけての江戸近郊では江戸時代後期頃には、既に梨の栽培が盛んだった事がわかっている。
明治時代には、現在の千葉県松戸市において二十世紀が、現在の神奈川県川崎市で長十郎がそれぞれ発見され、その後、長らくナシの代表格として盛んに生産されるようになる。一時期は全国の栽培面積の8割を長十郎で占めるほどであった。また、それまでは晩生種ばかりだったのだが、多くの早生種を含む優良品種が多数発見され、盛んに品種改良が行われた。
20世紀前半は二十世紀と長十郎が生産量の大半を占めていたが、戦後になると1959年に幸水、1965年に新水、1972年に豊水の3品種(この3品種をまとめて「三水」と呼ぶこともある)が登場し普及した。そのため、現在では長十郎の生産はかなり少なくなっている。