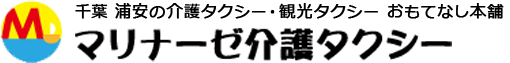松戸市
春風亭昇々、イケメン落語家が手作り“教科書”で歩むスタンダードの道のり
「思い通りに落語をやりたいだけなんです。思ったように表現して、自由自在にできるようになりたいんです」落語家・春風亭昇々(33)はこう言った。つぶらな瞳と整った顔立ちで“イケメン落語家”と紹介されることが多い。
「イケメンと言われることはどうでもいいですね。それによって『何だよイケメン落語家って』とか『そんなにイケメンじゃないじゃん』とか言われるんです。色んな人から言われるとショックを受けるんです。普通の顔の人は『変な顔だな』とか言われないじゃないですか。俺はその都度、色んな人から言われるんだって」と笑った。イケメンとして受ける取材も多い。「戦略的にやっていないです。ふざけてやっているところもあります。何でもいいやって」。女性ファンが多いことにも「本当はおじさんだとか、同世代の男の人に来て欲しいんですけど…」と話した。
浅草演芸ホールで口演する春風亭昇々
■落語の“教科書”づくり
昇々はコツコツと落語に向き合ってきた。手がける新作は骨太で、時折“狂気”も感じさせる。
「ボクは落語が不得意なんです。前座さんの方が俺よりうまいときがあるし、うまく出来ない時もあるんです」と言い切った。二ツ目昇進直後、自身の高座を撮影してみた。「ビデオカメラを買って、撮ってみたら全然思っていたのと違う。上下が出来ていないし、びっくりするくらいヘタクソだった。(前座で)4年やってきてすべてが出来ていない。愕然(がくぜん)としました」頭の中で思い描いていたイメージとの大きな乖離(かいり)に戸惑った。
先輩落語家の映像を研究した。「この人はマクラの時に0・5秒に1回首を振るけれど、何も言われていないからいいんだな」。細かい所作に自分なりの基準を決めた。「マニュアルが全部あります。どういう姿勢で座ればいいとか。座ってからどの位置に手を置く、どれだけひじを開く、肩を落とさないといけないとか」。上下ではどの場所に目線を向けるか、しゃべる時は眉間にしわを寄せないようになど、チェック項目をひたすらメモに起こした。自身の“教科書作り”だった。「みんなは頭で考えないで出来るんです。野球選手だって投げる時に“ひじの位置がここ”とか考えて投げていないと思います。でも自分は考えないと出来ないので…」。迷った時に立ち返る“原点”を記すことにした。
「ボクは精神が弱いのでウケなくて、否定されると落語のやり方が分からなくなるんです」。2015年のNHK新人落語大賞の決勝だった。前に出た4人が緊張しながら高座を終えると、昇々は「俺を見とけ」と心でつぶやき自信満々に高座にあがった。結果は5人中最下位だった。「点数は低かったですね。独りよがりで、うぬぼれだったということですよね」。再び“教科書”に立ち返った。日々の高座で気がついたことをメモにして加えていたものを再確認した。翌年は1位タイの投票数を獲得。決選投票となり1票差で惜しくも大賞は逃したが、健闘を見せた。
■師匠・昇太との出会い
大学4年になり、普通に就職活動をしようと思っていた時、春風亭昇太(58)の落語に出会った。友人から「面白いから」とビデオを貸してもらい読売テレビ「平成紅梅亭」での昇太の高座を映像で見た。「壺算」だった。落研に所属していた昇々は「古典落語は古くせえな、と思っていて好きじゃなかったんです」。だが、映像を見て面白さに笑い転げた。昇太が新作もやっていることもあり、入門を決意した。
07年の正月初席だった。新宿末広亭の楽屋口で昇太の出待ちをした。出て来ると声をかけた。「すごく面白かったです」ずっと出待ちをしていたので当日の高座は見ていない。「関西から来たんです」とたこ焼きせんべいを差し出すと、昇太はファンだと思ったのか手ぬぐいをくれた。「師匠の性格を考えて改まった感じではなくニコニコと話しました」。しばらく会話を続けたが、どうしても弟子入りは言い出せなかった。
2日後に再び訪ねた。「実は噺家になりたくて」と弟子入り志願をすると昇太は「連絡先教えて。連絡するから」。履歴書を渡した。1か月後に電話があった。「今、横浜の関内ホールにいるんだけど来られる?」。兵庫にいた昇々は新幹線に飛び乗り駆けつけた。 昇太は当時、弟子を取っていなかった。何人もの若者が志願に来たがすべて断っていた。三遊亭小遊三(71)に弟子を取りなさいと諭されていた。昇太は「面倒くさくて嫌だなと思ってみんな断っていたけれど、(小遊三)副会長から『お前も柳昇師匠に取ってもらったんだから、取らなきゃダメだ』と言われて、そうだなと思った」と当時を振り返る。「昇々なんて(入門志願が)その直後ですからね。タイミングが良かった」。昇々は自分の持っている運にも感謝した。「色々な偶然が重なったおかげですね」。
ソーゾーシーの公演を終え瀧川鯉八と笑顔の昇々(左)
■仲間が破門にされる
ほぼ同時に入門した“先輩”がいた。「広瀬君といって、ずっと(入門を)お願いしていたみたいで、2人で入ることになりました。広瀬君が1番弟子でボクが2番弟子」。だが、すぐに姿を消した。「広瀬君は着物がたためなかったんです。師匠が直接教えてくださったけど、出来なくて」。数日間、同じように教えても進歩がなく、破門になった。「『広瀬君を戻してください』とお願いしたけど、ダメでした。師匠はすぐ破門にするんだとトラウマになりました」。
まだ、芸名もない段階での“事件”に、昇々はいつ自分も破門になるか…とおびえたが、師匠・昇太はやさしかった。「今思えば自分は何も出来ないやつでしたね。脱いだ靴をそろえなさいとか、師匠もそんなこと言いたくないと思うことばかり言われました」。楽屋入りの時も一緒に来てくれた。「(自分の)出番じゃないのに、付いてきてくれて、みんなに『弟子だから』って紹介してくれました。本当にありがたいです」
昇太は言う。「ボクは弟子に落語のことについては怒らない方針です。(怒るとしたら)取り組み方だとかですが、昇々は1度も怒ったことがないです。あいつの顔を見ていると言う気にならなくなるというか、注意する気がうせてくる」。
そんな師匠の元で伸び伸びと修業に励んだ。前座時代、後に「成金」メンバーとしても活動する昔昔亭A太郎(40)、瀧川鯉八(37)、笑福亭羽光(46)と4人で2か月に1回、新作落語の勉強会「ねじまわしの会」を開き、ネタをどんどん作っていった。
■落語以外でも“教科書”を…
徐々に注目を集め、メディア出演も増えた。「ポンキッキーズ」ではMCを務め、テレビリポーターやナレーションの仕事も舞い込んだ。「1つ1つ全部違う。また“教科書”がいるよと…。落語の教科書が使えないんで…」。自分なりの“教科書”づくりが始まった。ナレーションでは自分のクセを分析し注意するポイントをまとめた。「ラ行とナ行が重なると読みにくいので印を付けるとか、最初に出て来る『イ』が発音しづらいとか…」。台本にもびっしりと書き込みをして、仕事の前日や当日にも綿密にシミュレーションをして本番に挑む。
そこまでやる理由は何なのか。「心配性というかネガティブなんです。準備はすごいします。落語は一人でやるものですべったら自分の責任だけど、番組はスポンサーがいてプロデューサーがいて共演者がいて…。最後に“くぎ”を打つのがボクで、そこで失敗すると台無しになる」
表情豊かに演じる昇々
■ランニングと落語の共通点
4か月前からランニングを始めた。「落語がマンネリ化していて、自分を変えないと発展がないなと思いました」。1日に10キロを走る。1時間で走破し、速度も速い。「走るのには持久力と集中力が必要で、それを付けたいなと思った。落語にも通じます。それがないと緊張感もなくなってしまう。それはいいことではないんです」。昇々は「落語が死ぬ」という表現で説明を加えた。「自由自在に出来るときもあるけれど、緊張感がなくなると会話がただの言葉の羅列になってしまう。そうなって死んでいくんです」
「成金」での活動もマラソンにたとえた。「マラソンと似ているんです。(本来は)自分との戦いですけど、みんなと一緒に走っていると自分のタイムも一人で走っているより伸びるじゃないですか。そういう良さがあります。無意識での切磋琢磨(せっさたくま)ですよね」
そして続けた。「自分のペースを守ると心に思っていれば、切磋琢磨(せっさたくま)する人がいるのはいいことです。でも人に依存すると自分がなくなるんで、自分の走りをすることを心がけています」あくまでも自分のペース配分を心に刻んでいる。
■新作へのこだわり
昇々は古典も演じるが自ら創作した新作へのこだわりが強い。今でも鯉八、立川吉笑(34)、浪曲師・玉川太福(39)とともにユニット「ソーゾーシー!」を立ち上げ実験的な作品を生み出している。「古典は素晴らしいと思うけれど、新作もあっていいと思う。色んなものがあるから文化は発展していくんだと思います。もっとみんな新作をやればいいのにと思います。古典落語のようなものを作ろうと思ったらそう簡単にはできないけれど、小説も映画も無限にある。ストーリーが良く分からないものや、人によってとらえ方が違うものだって落語にしていいと思うんです」
奇をてらうつもりは毛頭ない。「自分だけ変わったことをして目立とうという気はないんです。ウチの弟弟子が坊主になっていたので、何でなのと聞いたら『みんな髪の毛が長いのでボクはあえて坊主にしています』と答えたんです。それには自分がないですよね。結局人に影響されていることじゃんって。人を見て決めるのは良くないと思うんです。異端にはなりたくない。異端と言われるのは正統派があるので(比較で)言われること。スタンダードを目指してやらなくてはいけないと思っています」
新宿末広亭、ソーゾーシーに出演した昇々
■究極の高座を求めて…
ランニングをしていると、時々、どんなに疲れていてもいつまでも走り続けられる“ランナーズハイ”のような感覚になるという。同じように高座でも充実した気持ちを味わう時がある。「ものすごく自由に出来て、ふざけて遊んで出来るときがある。思いがけないことを勝手に言って、それにお客さんがはまって乗ってくれるような時が…。そういう時が一番いいですね」。アスリートが“ゾーン”に入る感覚と似ているかもしれない。「20回に1回くらいですかね」。時折訪れるその感覚への“入り方”はまだ分かっていない。
今後、どのような道を歩んでいくのか。昇々はやや伏し目がちになりながらもはっきりとした口調で言った。「努力して頑張って考えてもがきながらやれば出来るようになる。何も出来ないやつでも考えて頑張れば出来るようになる。それを証明したいんです」。