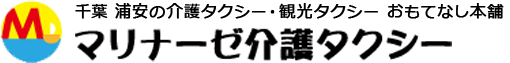生き残りへ…カーナビ正念場、市場伸び見込めず再編加速
カーナビゲーションシステムメーカー各社が岐路に立っている。パイオニアはカーナビ事業の業績悪化を受け、カルソニックカンセイなど他社との提携で経営の立て直しを模索する。アルパインやクラリオンも事業体制の見直しを進める。カーナビ市場は成熟し、今後は販売台数の大幅な伸びが見込めない。自動運転やコネクテッドカー(つながる車)向けの次世代技術への対応が急務だ。生き残りをかけた戦いが本格化する。
パイオニアが業績低迷から抜け出せない。2018年3月期の連結決算は自動車メーカーに直接供給するカーナビのOEM(相手先ブランド)生産事業の収益が悪化し、2期連続で最終赤字に落ち込んだ。
6月には森谷浩一社長率いる新経営体制が発足。他社との提携によるOEM事業の切り出しなどを視野に、秋ごろまでに改革案を発表する。6日に発表した18年4―6月期の決算短信には、「継続企業の前提に重要な疑義が生じている」と記載されるなど、事業の立て直しは待ったなしの状況だ。
パイオニアの業績が悪化したのは、17年3月期に量産を始めたOEM向けカーナビの開発費用が想定以上に膨らんだ影響が大きい。受注当初には要求されなかったコネクテッド機能の追加を中心に、度重なる仕様変更への対応に追われ、「莫大(ばくだい)な開発費を費やさざるを得なくなった」(小谷進会長)。
完成車各社はここ5年の間に、スマートフォンとカーナビの連携機能といったコネクテッド機能の採用で車の付加価値を高める戦略にかじを切った。パイオニアはこうした動きを先読みし、対応するだけの体制が十分に整っておらず、車のIT化への見通しが甘く準備が足りなかったことも事態を悪化させた。
足を引っ張るOEM事業の提携先候補として名前が挙がっているのがカルソニックカンセイだ。カルソカンは17年に日産自動車から独立し、米コールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)の傘下に入った。
日産以外への販路拡大や次世代コックピットの開発など新分野を強化している。カルソカンにとってはパイオニアが持つ完成車メーカーへの販路、カーエレクトロニクスの技術などを活用できる利点があるとみられる。
パイオニアの業績不振は、他のカーナビメーカーにとって人ごとではない。スマートフォンの普及などを背景に、車に後付けする市販向けのカーナビ需要が減少傾向にあるほか、OEM向けではCASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)と呼ばれる自動車の新潮流への迅速な対応が求められている。100年に1度と言われる変革期に入った車産業で生き残るには、カーナビに続く新しい収益の柱を育てる土台作りが欠かせない。
実際、アルパインは親会社のアルプス電気と19年1月に経営統合することを決めた。営業や開発、部品調達などの効率化を図り、車載事業拡大や収益性向上を狙う。
クラリオンは従来型カーナビの開発機能を日本から中国に移管することや、人員削減・再配置を柱にした構造改革を打ち出した。
業界再編の動きも目立つ。17年には韓国サムスン電子が車載事業強化に向け米ハーマンインターナショナルを買収した。デンソーはデンソーテン(旧富士通テン)を子会社化。カーナビのほか車載ECU(電子制御ユニット)、ミリ波レーダー事業で連携する考えだ。
トヨタグループではアイシン・エィ・ダブリュもカーナビ事業を手がけており、今後グループ内での事業再編に発展する可能性もある。
これに対し、渦中のパイオニアはカーナビの基本構造の開発で協力する三菱電機が筆頭株主。OEM事業見直しの内容によっては、三菱電機との資本関係が変化しそうだ。
次世代車対応を急ぐ
各社がカーナビに次ぐ将来の収益源にしようと経営資源を集中させているのが自動運転やコネクテッドをはじめとする次世代車向けの新技術開発だ。
パイオニアは自動運転用センサーと地図事業で巻き返しを図る。開発を進めるレーザーレーダー「3D―LiDAR(ライダー)」は、レーザー光で車の周辺を細かく検知する高機能センサー。レーザーディスク事業で培った光学技術を生かし、最終的には手のひらサイズで1万円を切る価格に仕上げ、他社と差別化する。地図事業では17年にオランダの地図大手ヒアと資本提携しており、自動運転用高精細地図の提供や地図を導入しやすい環境を整備する。
クラリオンは車載カメラがとらえた映像を高精度に処理する技術を応用した自動駐車技術の開発を強化する。直近では日産自動車の電気自動車(EV)「リーフ」に自動駐車用ECUが採用された。親会社の日立製作所や日立オートモティブシステムズとの連携を強めており、指定した敷地内を完全自動走行し駐停車する「自動バレーパーキングシステム」の実用化を目指す。
カーナビ各社は音響や映像、ソフトウエアといったエレクトロニクス技術を持つのが強み。自動運転車やコネクテッドカーが主流となり、カーナビのデザインが変わっても、ドライバーに必要な情報を正しく伝達するインターフェースはなくならない。車内で音楽や映像を楽しむプライベート空間としての利用が一層広まる可能性もある。
JVCケンウッドの野村昌雄取締役は、「車メーカーを納得させられる技術提案力がより問われる」と生き残りの勘所を指摘。100人規模のデザイン会社を持つ強みを生かし、ドライバーが見やすいヘッドアップディスプレーなどへの情報表示を提案する活動を積極化している。自社技術の強みを見極め、次世代車の開発を急ぐ完成車メーカーに有益な提案を行えるかが勝負になる。